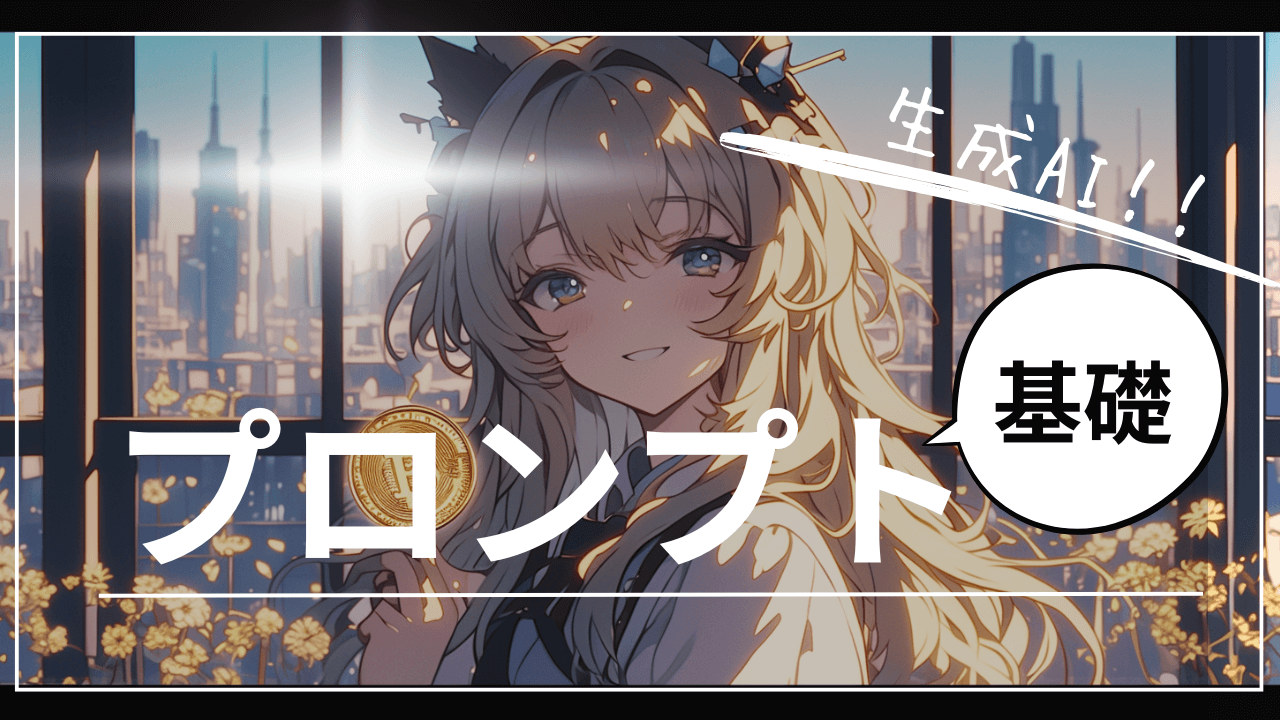「生成AI、便利って聞いて使い始めたんだけど、なんか期待した感じじゃないし、思い通りに使えない…」
そんな風に感じたこと、ありませんか?実は僕も最初はそうでした。
「そういうことを聞きたいわけじゃないんだけど?」みたいな回答が返ってきたり、そもそも全然使える回答になっていないこともしばしば。
でも、安心してください!生成AIはどんどん進化して初期の頃とは比べ物にならないほど性能が上がっているので、コツを知れば、驚くほどスムーズに思い通りのアウトプットが得られるんです。
今回は、僕がChatGPTが出現した時から実際に使って学んだことや、仕事で生成AIの業務活用に携わる中で得た知識をもとに、生成AIでのプロンプトの書き方(基礎編)を紹介していきます。
生成AIを使いこなして高品質な回答を出すのに邪魔になる「思い込みの解消」から始めて、「プロンプト作成の基本」まで、初心者でも今すぐ実践できる簡単なテクニックをご紹介します。
この記事を読むと…
- 生成AIを使いこなす上で邪魔になる思い込みを解消できる
- 生成AIのプロンプト作成の基本がわかる
- 初心者でも使える具体的なコツを学べる
なお、まだ生成AIを使ったことのない方がいれば、下記記事から無料でChatGPTを使えますので、ぜひ試してから本記事をお読みいただくと、より理解が深まるかと思います。

そもそも生成AIの「プロンプト」とは?
そもそも、プロンプトという言葉に馴染みのない方もいると思います。
生成AIを使うときに絶対外せないのが、「プロンプト」という指示文。簡単に言うと、AIに「こんなことをしてほしい!」と伝えるためのメッセージです。
例えば、以下のような指示文がプロンプトです。
- 「京都での3日間の旅行プランを考えて!」
- 「メールの返信文を丁寧な口調で書いて」
こうしたプロンプトを受けて、生成AIは結果を生成してくれます。
で、プロンプトの書き方次第で、生成される結果の質は大きく変わります。
カレーを作りたい時に、食材とかレシピが重要なのと同じイメージです。
仕事で考えると、ちゃんと無理のない、的確な指示を出せる有能な上司の方が、部下の力を引き出せるのと同じ。
この「高品質な指示=プロンプト」を作る技術のことを「プロンプトエンジニアリング」なんていったりもします。
生成AIを使いこなすにはプロンプトエンジニアリングが必要??
ということで、ここまで読んでくれたあなたは生成AIを使って良い回答を生成するには「プロンプトエンジニアリング」が必要なんだ!と感じたでしょう。
こういう書き方をしておいて申し訳ないんですが、実はそれ、ちょっと違います。
ここはかなり重要なパートで、生成AIを使いこなせないと悩んでいる人の多くが陥っている思い込みだと思います。
この思い込みを解消せずにいくらプロンプトの書き方を学んだところで、結局はあまり効果がないのは、僕の実体験で認識済みです。
ということで、すらすらっと読めるようにまとめたので、ちょっと読んでみてください。
プロンプトの書き方を学ぶ前に超重要な「生成AIを使いこなすのに邪魔になる思い込み」を解消していきましょう。
生成AIを使いこなすのに邪魔になる「思い込み」4つ
Aあなたは、もしかすると次のような思い込みを持っていませんか?
- 生成AIを使うにはまず使い方を覚える必要がある
- 生成AIのプロンプトには文法がある
- 生成AIの回答結果の品質はプロンプト次第である
- 生成AIのプロンプトはテンプレに沿って書くと回答結果の品質が上がる
どれも当たり前に見えますが、僕が実際に生成AIと向き合ってきた中で、ちょっと違うなと感じたのが上記4つです。
これらの思い込みが、実はAI活用の妨げになっている可能性があるので、一緒にリセットしましょう。
思い込み①:生成AIを使うにはまず使い方を覚える必要がある
生成AIに決まった使い方は無い!
生成AIは、新しく買った洗濯機とかソフトウェア、アプリケーションのように説明書を読まないと使えないツールではありません。
むしろ、英語を喋るのと似ています。習うより慣れろ、です。
実際に試しながら上達するのが生成AIであり、使い方を細かく覚えるよりも、どんどん使って慣れることが大切です。
思い込み②:生成AIのプロンプトには文法がある
プロンプトに決まった型は無い!
英語は細かい文法が多少間違っていても通じます。
生成AIも同じで、細かな表現の違いで大きく回答が変わるわけではありません。
プロンプト作成に細部までこだわる必要はなく、大枠さえ掴めればあとは実践で十分です。
思い込み③:生成AIの回答結果の品質はプロンプト次第である
生成AIの回答品質を上げるのは、プロンプトだけじゃありません!
実は、AIの回答品質は「モデルの性能 × プロンプトの工夫」で決まります。
で、生成AIの回答品質は、プロンプトの質よりも、AIモデルそのものの性能に大きく影響されます。
もしあなたが何度もプロンプトを修正しても満足な結果が得られないのであれば、より高性能なモデルを選ぶほうが手っ取り早く品質を上げられます。
昔と違い生成AIの読解力も上がっていますし、あなたのプロンプトは実は90点くらいあるということも多いので、プロンプトで無理に100点を目指すよりも高性能なモデルにしちゃった方が良い結果が得られます。
思い込み④:生成AIのプロンプトはテンプレに沿って書くと回答結果の品質が上がる
ここが一番重要ポイントです!生成AIのプロンプトテンプレートは背水の陣です!
世の中にはプロンプトテンプレートが数多く公開されていますが、「テンプレを使えば高品質な回答が得られる」というのは少し誤解です。
テンプレートが必ずしも有効でない理由は、そのテンプレがあなたのタスクに十分特化していないからです。
たとえば「メールを送る」というタスク一つでも、送信先や目的によって必要な内容は全然違いますね。
プロンプトは、具体的であればあるほど回答の品質が上がります。
テンプレートや文法なんかよりも、この「特化の程度」=「粒度」をどこまで追求できるかが重要です。
例えば、世の中のテンプレートで、あなたがAIに頼みたいタスクを超具体的に指示してくれているものなんて、存在しないですよね?
これは言い換えると、世の中に出ているテンプレートは「粒度」が浅すぎて、あなたが求める回答品質には到達しないということです。
部下へ何かを依頼する時にどんな依頼方法がベストなのかは毎回変わります。
生成AIもそれと同じで、プロンプトテンプレートを使ったとしても、あなたが生成AIにやらせたい指示に合わせて調整が必要なのです。
【参考】プロンプトのテンプレートが役に立つタイミングは?
ちなみに、プロンプトテンプレートが役に立つのは、定型的で繰り返しが必要な作業の時です。
順番としては下記のように「良いプロンプトを作る」→「テンプレート化」という流れです。
- タスクが生じる
- タスクに特化したプロンプトを書く
- AIに投げて回答を得る
- 回答に満足できなければプロンプトを修正し再度AIに投げる
- 良いプロンプトができたら記録する
- (繰り返すタスクの場合のみ)プロンプトをテンプレ化する
結局のところ、テンプレートは叩き台くらいにはなりますが、”生成AIの回答品質を高めてくれるものでは無い”というところが重要ポイントです。
プロンプトテンプレートを使う意味は回答品質の「均一化」
テンプレートを使う最大のメリットは「回答結果の品質を均一化する」ことです。
テンプレは回答品質を高めるためではなく「毎回一定の品質を確保する」ためにあるのです。
これは、テンプレートに従うとAIの回答の自由度が下がり、毎回同じような品質の回答が得られるからですね。
生成AIのプロンプト作成のコツ
というわけで、こちらが生成AIを使いこなす上で解消したい思い込みでした。
- 生成AIを使うにはまず使い方を覚える必要がある
→習うより慣れることが大事 - 生成AIのプロンプトには文法がある
→プロンプトに決まった型は無い - 生成AIの回答結果の品質はプロンプト次第である
→モデルの性能の方が回答品質に大きな影響 - 生成AIのプロンプトはテンプレに沿って書くと回答結果の品質が上がる
→テンプレは回答品質を上げるためのものではない
ここらへんを頭の片隅に置きつつ、この先を読んでもらえるとプロンプトの使い方がグッと上達しやすくなると思います。
では、いよいよプロンプト作成の具体的なコツを解説していきましょう。
プロンプトを作る上で気をつけたいのは、「AIにとってわかりやすい指示を出すこと」。
例えば、以下の通りです。
- 何をしてほしいのか(目的やタスク)を明確にする
例:「新製品の特徴を箇条書きで説明して」 - どんなスタイルで答えてほしいのか(トーンや形式)を指定する
例:「軽い口調でわかりやすく説明して」 - 背景情報や制約条件を伝える
例:「初心者向けで、専門用語は使わないで」
1. 具体的に指示を出す
まずは、曖昧な表現を避けることです。例えば、
- 悪い例:「簡単な旅行プランを作って」
- 良い例:「2泊3日で京都を訪れる旅行プランを作って。移動は電車で、予算は1日1万円以内にして!」
良いプロンプトとは、誰が読んでも「これをしたいんだな!」とすぐに理解できるものです。
AIも同じなので、あなた以外の他人が見てもちゃんと理解できるプロンプトを作ることが重要です。
2. 背景やコンテキストを設定する
AIは、背景情報があるとより良いアウトプットを生成してくれます。例えば、
- 悪い例:「クリスマスについて教えて」
- 良い例:「あなたは小学校の先生です。小学生に向けて、クリスマスの伝統をわかりやすく説明してください。」
誰に向けたものなのか、どんな役割で回答してほしいのかを具体的に設定するのがポイントです。
3. 出力形式を指定する
生成AIは、アウトプットの形式を指定することで、より使いやすい結果を提供してくれます。例えば、
- 「箇条書きにして」
- 「HTMLコード形式で出力して」
- 「1分で読める長さの文章にして」
こうすることで、結果がそのまま自分の使いたい目的に応じて使える形になるので便利です!
プロンプト作成の具体例
具体的な場面や目的を考えながら、プロンプトの簡単な例を見てみましょう。
1. 何かを言い換えるプロンプト
目的: 普通の人には難しい専門的な内容をわかりやすく説明したい
- 例:「一般相対性理論では、時間と空間は相対的なもので伸び縮みすると言われていますが、全くイメージが湧きません。そもそも見えないし感じないものが理解できないので、実際にあるものを使って理解できるように説明してください。」
ポイント: 指示の具体性に注意し質問の背景を説明、出力形式の正解はわからないので触れていません。
効果: 専門的な内容や、自分が知りたい内容について、わかりやすい表現で教えてくれます。ネットや本の知識は小難しい情報も多く、説明する気あるの?って情報もありますが、それらの理解を助けてくれます。
2. フォーマットを指定したプロンプト
目的: 出力結果をそのまま何かに利用したい
- 例:京都のおすすめ観光地を、以下のフォーマットで箇条書きにしてください。
- 名前
- 特徴
- 見どころ
ポイント: 出したい出力形式が決まっているので、具体的に指示しています
効果: 出力結果をそのままコピーしてどこかに利用できます。1から自分で作ることも出来ますがめんどくさいし時間がかかります。けれどAIなら第一案を瞬時に作ってくれるので、僕は手直しするだけでOK。かなり効率的です。
3. 思考法を指定したプロンプト
目的: アイデア出しやクリエイティブな発想を得たい
- 例:「固定観念にとらわれない新しいマーケティング戦略を考えてください。予算は少なめで、SNSを活用した方法を重視してください。」
ポイント: 自分じゃ浮かんでこない思考を生成AIに任せています。自由すぎても役に立たないので、制約条件を明示することで、現実的かつ役立つ提案が得られます。
効果: 人間一人の思考力は限界がありますが、AIはあの手この手で色んな思考パターンを実行してくれます。合わせて自分も考えることで良いアイデアが浮かぶ回数が格段に増えました。
4. 自分と異なる視点を取り入れるプロンプト
目的: より多角的な情報を得たい
- 〇〇というアイデアを思いついたんですが、懸念点はありますかね?考え損ねている観点や、このアイデアに同意できない人たちの考えを聞きたいです。
効果: 自分の思考のクセを取り払った検討が出来ます。
日常をちょっと楽しくする生成AIの使い方、集めました
プロンプトの書き方というか、そもそも生成AIの使い道がそもそも浮かばない!という方も多いはず。
なので、最後に僕が日常生活で生成AIを使っている場面をずらっと紹介してみます。
正直アイデア次第で生成AIはどんなことにも応用できる可能性があります。
色んな場面で「これめんどくさいな」と思ったら生成AIが使えないかを考えてみるのがお勧めです。
生成AIの日常での使い道まとめ
というわけで、ずらっと並べてみました。
- 今日の献立、もう考えたくないとき
- LINEの返信、気まずい・めんどくさいとき
- 旅行のプラン、ざっくり立ててくれる
- 子どもの自由研究、テーマが出てこないとき
- SNS投稿の文章を一緒に考えてくれる
- ブログ記事の構成を考えるのがラクに
- ブログの冒頭で読者を引き込む導入文
- メルマガ・LP文のたたき台を作ってくれる
- キーワード調査・競合リサーチの時間を圧縮
- Excelで毎回同じ操作してるとき
- プログラミングコードを書いて自動化アプリを作っちゃう
- 自分の代わりにプロンプトを書いてくれる
一番効果が高いのはやっぱり副業のハードルが下がることですがね。
それぞれの詳しい内容や、「自分で使い道を考えて日常を便利にする!」テクニックは以下の記事でもっと詳しく解説しておりますのでぜひ!
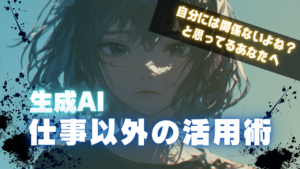
まとめ:生成AIを使いこなして生活を豊かにしよう!
今回は、僕がChatGPTが出現した時から実際に使って学んだことや、仕事で生成AIの業務活用に携わる中で得た知識をもとに、生成AIでのプロンプトの書き方(基礎編)を紹介してきました。
今は難しく感じられるかもしれませんが、少しでも新しい知識を得られたと感じてもらえたら嬉しいです。
もしまだ生成AIを使ったことのない方がいれば、下記記事から無料でChatGPTを使えますので、ぜひ試してみてください。

今回は以上です。