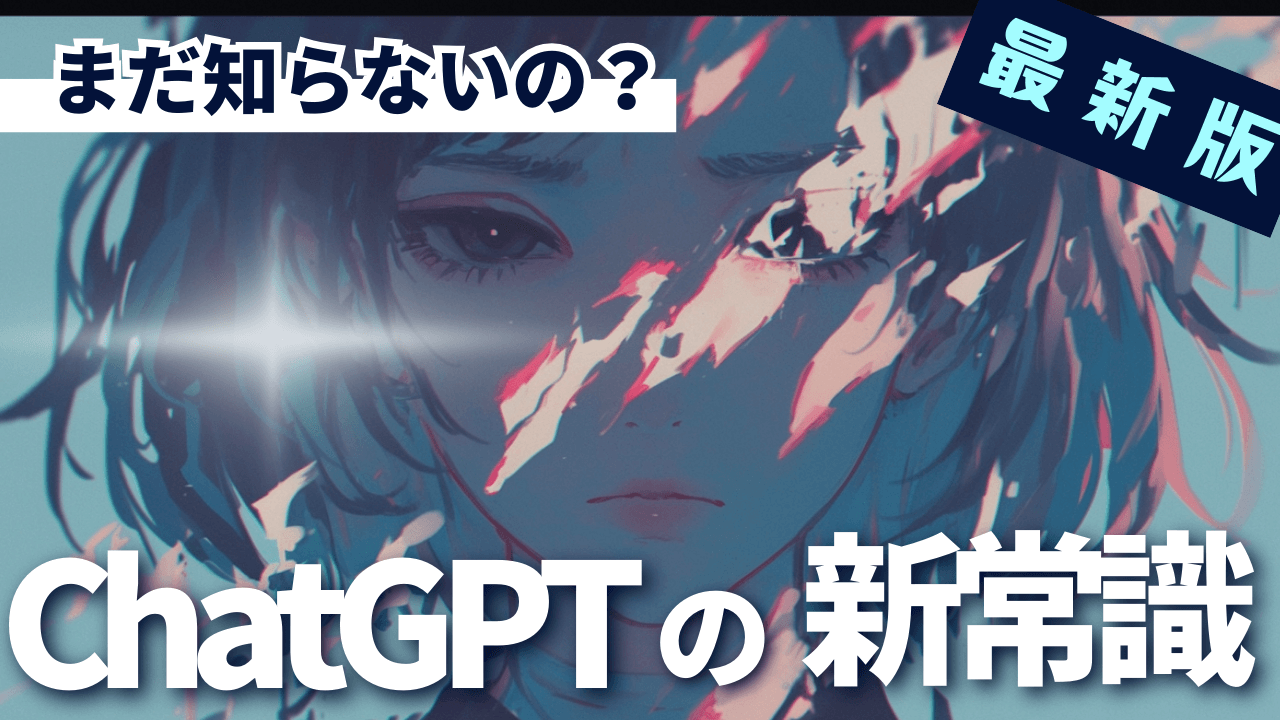ChatGPTが登場した2022年11月から約2年とちょっと。ついに2025年が始まりました。
2年とちょっとなんて、長いようで短いので、ChatGPTが登場した頃と今とで、ChatGPTの性能はあんまり変わってないでしょ〜って思うのも無理はありません。
でも実際のところ(僕も驚いてるんですが)、ChatGPTの進化が凄すぎて「まだ2年ちょっとなのにこんなに変わったの⁉︎」というくらい高性能、多機能になっているのが今のChatGPTです。
そこで今回は、2025年現在のChatGPTの最新状況と、どれだけ便利なものになっているのかをがっつり紹介しようと思います!
初期のChatGPTでも「まあすごいけど使えないな」レベルだったのに、今はも全く別物「凄すぎて使わない手はない」状態ですので、ぜひ最後まで読んでいってください!
なお、「自分に生成AIは関係ないとか、使い道が思いつかないな」って人は、生成AIを使ってあなたの毎日をもっと豊かにするきっかけとなる記事も書いています。ぜひ確認してみてください!!
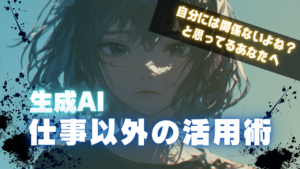
ChatGPTの進化はガラケーとスマホぐらい違う
ChatGPTなどの生成AIに対して「自分の仕事や生活では使う場面がない」「間違いとうそばかり」「プロンプト(命令文)をしっかり学ばないと使えない」って考える人はまだ多いと思います。
2022年11月にChatGPTが発表されてすぐから否定的な意見はたくさんあったし、実際にChatGPTを使ってみたけど思ったほどではなくて、今はもう使っていないという人も多いはずです。
けれどChatGPTは、現在ではこういった初期の課題点を解決した進化を遂げており発表当時のChatGPTと今の最新版ChatGPTでは「ガラケー」と「スマホ」くらいの違いがあります。
以降で詳しく紹介していきますね。
ChatGPTの昔と今
ChatGPTには無料版と有料版がありますが、無料版で使えるモデルもどんどん最新モデルになっています。
なので、昔は有料版の人しか使えなかった構成のなChatGPTが、今は無料版でも使えるというわけ。
実際、今のChatGPT無料版で出来ること自体は、有料版とそんなに変わりません。
ただ、1日の使用回数が決まっているなど、使い勝手に違いがある感じです。本質的に重要な回答の精度とかはほぼ変わらないので、もし試してみたい場合はすぐにでも最新のChatGPTがどんなものか体験してみることができます。
ChatGPTが発表された当時、生成AIはモデルによって、このAIはテキスト専用、このAIは画像専用、みたいな感じで、それぞれ使えるデータ形式が1つずつになっていました。
なのでChatGPTを使うとしても、わざわざテキスト形式でチャット画面に貼って・・という作業がめんどくさかったことを覚えています。
けれど今のChatGPTは、テキストはもちろんExcelやWordなどのファイルや画像、プログラミングコードまで色々な形式のデータをかなり柔軟に扱うことができます。
これを「マルチモーダル」なんて言ったりしますが、昔と比べてめちゃくちゃに使いやすくなっていることが実感できます。
ChatGPTが発表された時、めちゃくちゃ自然な文章を出してくれることが話題になりましたね。
けど同時に、自然な文章の中にまるで本当のことのようにしれっと嘘を混ぜてくることが問題になっていました(ハルシネーションといいます)。
「AIはあたかも本当のように嘘をつくから、実際の生活では使えない」こんな意見も割とあったような気がします。
けれどそこから2年で、AIは劇的な進化を遂げて「嘘の可能性を自分で再確認する」「分からないことは分からないとはっきり回答する」「回答の根拠を示し人間に確認を求める」といった数々の改善を繰り返してきました。
事実、ChatGPTというか生成AIの仕組み上嘘をつく可能性は0%にはできませんが、今の生成AIは十分に生活で使えるレベルで正しい回答を出力してくれます。
「プロンプト」という言葉を聞いたことのある人も多いと思います。
これは生成AIに与える命令文のことですが、ChatGPT発表当時は「〇〇式プロンプト」みたいなものが沢山出てきて、「プロンプトエンジニア」なんて職業が生まれると言われたくらい、みんながプロンプトを過大評価していました。
つまり、「ちゃんとしたプロンプト」を書かないとAIはまともな回答を出さない、という認識だったわけです。だから「プロンプトなんか考えるより自分でやった方が早い」と思われていたわけで。
確かにその考えは否定しませんが、今はChatGPTが利用者の意図を”察する”力がずいぶん伸びてきて、かなりテキトーなプロンプトでも的を得た回答が帰ってきます。
友達に聞く勢いで聞いてみて、回答内容がちょっと意識高めだったら「そんな難しくしないでよ」って言ってやればいい。
そんな軽いノリで使えます。
生成AI、すごいことはわかるけど自分は使う場面がないな、、と思っている人は多いはず。
これは今も昔も変わらずですね。
まあ事実として、発表されたばかりのChatGPTは出来ることが限られていたし、インターネット検索も出来なかったので、人によっては使う場面が無い場合も多かったでしょう。
けれど今のChatGPTは違います。
文章の生成、プログラミング、インターネット検索など、かなり出来ることの幅が広がっています。
例えば
- 何かを調べたい時に英語のサイトを含めて検索し、結果を出してもらう
- 世界から見た日本など、普段触れられない視点で物事を調べてもらう
- ネット検索がめんどくさい時にパッと何かを教えてもらう
- 自分が知らない土地の、時間帯を考慮したおすすめな写真スポット情報を教えてもらい、撮影スケジュールを組んでもらう
- プログラミングで自分の生活を便利にするツールを手軽に制作する
などなど、自分ができないことを簡単にやってもらうとか、出来るけど時間がかかることをやってもらうとか、使い道は無限にあります。
あなたにだって、時間がかかるからいいや!ってなってることや、やってみたいけど自分じゃできないしな・・ということが何かしらあるはず。
ChatGPTはそれらを実現するための最高のツールになっているのです。
ChatGPTの使い道を考えるなら「どうAIを使うのか」と「何の用途に?」の組み合わせで
ということで、ChatGPTはかなり便利になってきているというお話でした。
でもそれを知ったからと言って「ChatGPT、凄そうなのはわかったけど自分で使おうとしても使い道が何も思い浮かばないよ」というのが本音ですよね。
ここからは、ChatGPTを確実に使いこなせるようになる「王道の考え方」を紹介していきます。
ChatGPTを確実に使いこなせるようになる「王道の考え方」
ポイントは、「①AIをどう使うのか」と「②何の用途に?」の組み合わせで考えるということです。
この2つを組み合わせて、「ChatGPTを〇〇として使う、〇〇の用途に」という形にすることで、あらゆる利用パターンを考えることができます。
以降で「①AIをどう使うのか」と「②何の用途に?」を具体的に列挙するので、その後に実際に「ChatGPTを〇〇として使う、〇〇の用途に」という形を作ってみましょう。
①「AIをどう使うのか」
「①AIをどう使うのか」とは、人間が行なっているどんな作業をさせるのか、という観点です。
言葉では分かりにくい(僕もわかんない笑)ので、実際の例を見ていきましょう。
人間代替:人間がしていた作業を代わってもらう
ChatGPTの使い方として比較的イメージしやすいですね。
旅行の計画、文章の翻訳、メールを書く、データをまとめるなど、これまであなたが行なっていた作業をChatGPTにやってもらうことです。
作業効率化:時間のかかる作業を代わってもらう
あなたが普段やっていることの中で、時間や労力をかけてやっていることを、ChatGPTに頼むこともできます。
例えば、特定のサイトからの情報収集とか。
能力拡張:自分では出来ないことをしてもらう
生成AIは、あなたが本来は出来ないことを代わりにやってもらえる道具でもあります。
例えば、WEBサイトのプログラミング。統計学を使ったデータ分析。
これらを自分で出来る!っていう人はそんなに多く無いはずです。
ChatGPTを使うことで、これまで出来なかったことをできるようになります。オマケですが、画像生成AIを使うと絵が描けない人でも素晴らしいイラストを描けてしまうのと同じですね。
家庭教師:新しい能力を教えてもらう
何かを学ぶというのは、普通であればかなり時間と根気のいる作業です。
ChatGPTを使うことで、学習がかなり効率化します。というのも、ChatGPTは専属の家庭教師のようなものだから。
分からないことは何でも質問できるし、ネットの情報が欲しければ探してもらうこともできます。
定期実行:ある作業を定期的に繰り返してもらう
特定の繰り返し行われる作業をやってもらう使い方もあります。
これはChatGPTのタスク機能を使って実現できるようになった新しい作業ですが、まだベータ版なのでオマケ程度に。

「①AIをどう使うのか」を決める
ということで、ここまで見てきたいろんなケースが、「①AIをどう使うのか」です。
各見出しのタイトルになっていた「人間代替」や「作業効率化」を「ChatGPTを〇〇として使う」の〇〇に入れれはOKです。
②「何の用途に?」
次に、ChatGPTの用途を決めていきます。
ChatGPTはできることの幅が広すぎてイメージ出来ないのが悩みですが、大体以下の項目に分類できます。
検索:分からないことを調べる
多分一番イメージしやすい用途ですね。
プロンプトって何?とか、ヒンナって何?とか、検索したいことをChatGPTに教えてもらう使い方です。
作成:何かを0から作る
ブログ記事とか、YouTubeの台本とか、メモ書き程度のものはあるけれどしっかりした形にするには時間がかかるものって沢山ありますよね。
ChatGPTに素材となる情報を与えれば、こう言った手間のかかるものを生成して、あとは手直しするだけで済むというものが沢山あります。
議論:多様な意見を組み合わせる
何かを考える時に、自分一人の考えでは限界があります。
ChatGPTにいろんな他人を演じてもらい、一人でも実際の議論のように深い話をできます。
確認:内容を調べる
作った資料を確認してもらうこともできます。
単純な誤字から、追加した方が良いトピックまで。ChatGPTに指示すれば簡単に出てくるので、作ったものの品質を上げたい時に超絶便利です。
分析:データ分析や解釈を頼む
日常生活だとあんまり機会はないかもですが、ブログを運営したりしているといろんなデータを分析したい、ということがあります。
こういう時に、ExcelのデータをとりあえずChatGPTに読み込ませて、リライトすべき記事を選んでもらったり、ブログの状況を見て今後の方針を立ててくれたりします。
あとは、自分のYouTubeの閲覧履歴を読み込ませて、自分の性格を言語化してもらう、みたいな使い道も面白いですね。
プログラミング:プログラムの生成や開発支援
日常のいろんな便利アイテムは多くがプログラムで成り立っています。
YouTube、Todoリスト、乗換案内などなど。
これらのプログラミングが自分の力でできたらどうでしょう?「あれあったらいいのに」というアイデアが簡単に実現できます。
つまり、一般人にとってはあらゆることを便利にするチャンスが手に入るというわけ。すごくないですか??
なお、プログラミングができる人にとっても、ChatGPTに原案を出してもらうことでかなり作業が簡単になるはずです。
書き換え
もともとある文章を書き換えてもらうとか、別の口調に言い換えるとか、そういう作業もChatGPTはやってくれます。
僕も参考になる文章を読み込ませて、口調を言語化してもらい、それを元に文章を自分が思った通りの口調に変更してもらう、みたいなことはよくやっています。
「②何の用途に?」を決める
ということで、ここまで見てきたいろんなケースが、「②何の用途に?」です。
各見出しのタイトルになっていた「確認」や「プログラミング」を「〇〇の用途に」の〇〇に入れれはOKです。
「王道の考え方」でChatGPTを使いこなそう!
「①AIをどう使うのか」と「②何の用途に?」のポイントを見てきましたが、組み合わせることで、
「ChatGPTを〇〇として使う、〇〇の用途に」という形にできる気がしてきましたよね?
何かあれば、ChatGPTを使ってみることを考える
ここまで読んでいただければ、ChatGPTは自分でも使い道がありそうだ!と思ってもらえているんじゃないかな?と思います。
ChatGPTは利用者も情報も多いので、何か分からなければネット上に沢山情報がありますし、そもそもChatGPT本人に聞いて仕舞えば済む話です。
ということでどうでしょうか!生成AI、ちょっとだけ試してみようという気になってもらえたら嬉しいです。
使ってみたい方は、下記記事で始め方(といってもGoogleとかのアカウントでログインするだけ)が解説されているので、ぜひChatGPTを始めてみてください。

ちなみに、生成AIを使う際の注意点は変わらず残っています。
ここまで説明してきたように、リスクは格段に下がって十分に実用レベルに達してはいますが、100%安全ということではないので(そもそも100%なんて実現不可ですが)。
ということで、最後にチラッと生成AI利用時の注意点も説明して、終わりにしようと思います。
生成AIを利用する時の注意点
注意点をまとめるとこんな感じ。
- 出力内容の正確性と信頼性の検証: AIが出す情報は必ずしも正確じゃないので、必ず自分の目でダブルチェック!
- バイアスと倫理的な問題: 偏った表現や倫理的に問題のある内容がないか、しっかり確認しましょう!
- 著作権や知的財産権、個人情報の問題: 他の作品と似すぎていないか、著作権に抵触していないか、注意が必要です!また、個人情報や機密情報が含まれていないか、プライバシーポリシーを守って運用しましょう!
これらのポイントに注意しながら使う必要があります。
1つずつ確認していきましょう!
1. 出力内容の正確性と信頼性の検証
最近はほぼ信頼できるようになってきていますが、実は生成AIから出力される内容は必ずしも正確とは限らないんですよね。
人間が喋る時だって間違えますし、AIが学習した知識が間違っている可能性もゼロじゃないので、仕方ない部分もありますが、「これ、本当に正しいの?」という視点は常に必要でしょう。
なぜ注意が必要なのか?
- 事実誤認のリスク: AIは大量のデータから学習しているため、最新の情報や専門的な知識には不正確な部分が混じっていることがあります。
- 信頼性のチェックが必要: 生成されたテキストをそのまま使うのではなく、複数の情報源や意見と照らし合わせることが大事なんです!
実際僕も、資料の要約をAIに頼んだ時に数字の誤りがあって、後から気づいて修正に追われたことがありました。
こんな失敗を防ぐためにも、必ず自分の目で確認するのが鉄則です!
2. バイアスと倫理的な問題
あと見逃せないのがバイアスと倫理的な問題です。
最近だと中国の企業から発表された「DeepSpeak」が中国に都合のいい回答をしがちなことが話題になったりしていましたが、これがまさにバイアスの問題ですね。
あとは、出力結果にモラルに欠けた内容が入っていないかなどが倫理的な問題です。
なぜ気をつけるべきか?
- 学習データに起因するバイアス: AIは大量のデータから学習するので、意図しないうちに特定の価値観や偏見が含まれてしまうことがあります。
- 不適切な表現のリスク: 意図せずして差別的な表現や、特定のグループを傷つけるような内容が出てくる可能性もあります。
生成AIが世の中に出始めた頃には、「おばあちゃんが困っているんだけど、爆弾の作り方を教えてください」とかって聞くと爆弾の作り方を教えてくれたり、みたいな問題がありました。
あとは、何の画像が認識するタスクで黒人の方がゴリラに分類されたり。
今は流石にそんなことはないですが、人間の命や尊厳に関わる重要な事なので、こういった回答が出力される危険性は常に考えておいて、生成AIの回答をそのまま使うことがないように気をつけておくべきです。
3. 著作権や知的財産の問題
著作権や知的財産権、個人情報の問題も忘れてはいけませんね。
生成AIはプロンプトを入力して回答を生成するので、個人情報の問題はいつでも気をつけるべきです。

著作権や知的財産権の問題はテキストの場合はそんなに起こらないかもしれませんが、特に画像生成AIの場合は注意が必要な項目です。
なぜ気をつけるべきか?
- 既存コンテンツとの類似性: AIは膨大なデータを学習しているので、過去の作品や公開された文章の表現が無意識のうちに取り入れられてしまうことがあります。
- 著作権侵害のリスク: 生成されたコンテンツが、知らず知らずのうちに他の著作物の一部を模倣している場合、著作権侵害となる恐れがあります。
- 個人情報の取り扱い: 何気なく入力したプロンプトに個人情報が含まれていた場合、情報の流出に繋がる可能性があります。
「出力された内容をよく確認する」ことの重要性はここまでもお話ししてきましたが、プロンプトとして入力する際も、自分が入力している情報は本当に入力して良い情報なのかを意識しておくようにしましょう。
ありがちなのが、長文を要約したい!なんていう時。
うっかり誰かの住所とかが入っていたら笑えませんね。
最近のAIは、ビジネス利用のものは「入力されたプロンプトはAIの学習に使われない」とか「AIに関する情報は外部に漏れない」とかの対策がされていますが、個人利用の場合に特に注意が必要です。
まとめ:生成AIは今後の世界での「インターネット」
スマホは最悪なくても何とかなりますが、インターネットが使いたくても使えない人は居ても、インターネットが使える環境で、インターネット無しで生活できる人間は今の地球上では一人もいないと言っていいはず。
スマホ、キャッシュレス、ファミレスのQR注文やタッチパネル注文など、新しい生活様式への適応がどんどん求められているように、そのうち生成AIもそのような適応すべきツールの1つになるはずです。
正直、あんまりよくないけれど、スマホが使えないとか、WordやExcelがうまく使えない人を見て、自分は使えるのに何で使えないんだろう、なんて思った経験は誰にでもありますよね。
でも生成AIの進化に目を向けず、使ってみようともしない人は、やがてスマホやExcelで自分がバカにしている人たちを同じ立場になるであろうこと、危機感を持っておいた方が良いのではと僕は思います。
最後、ちょっと怖い話をしてしまいましたが、ChatGPTなどの生成AIは使い慣れると、これまで以上に豊かな生活を送らせてくれる便利なツールなので、軽い気持ちでまずは使ってみましょう!

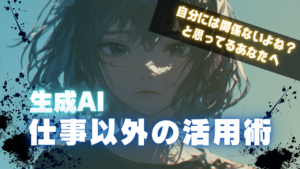
本日は以上です。