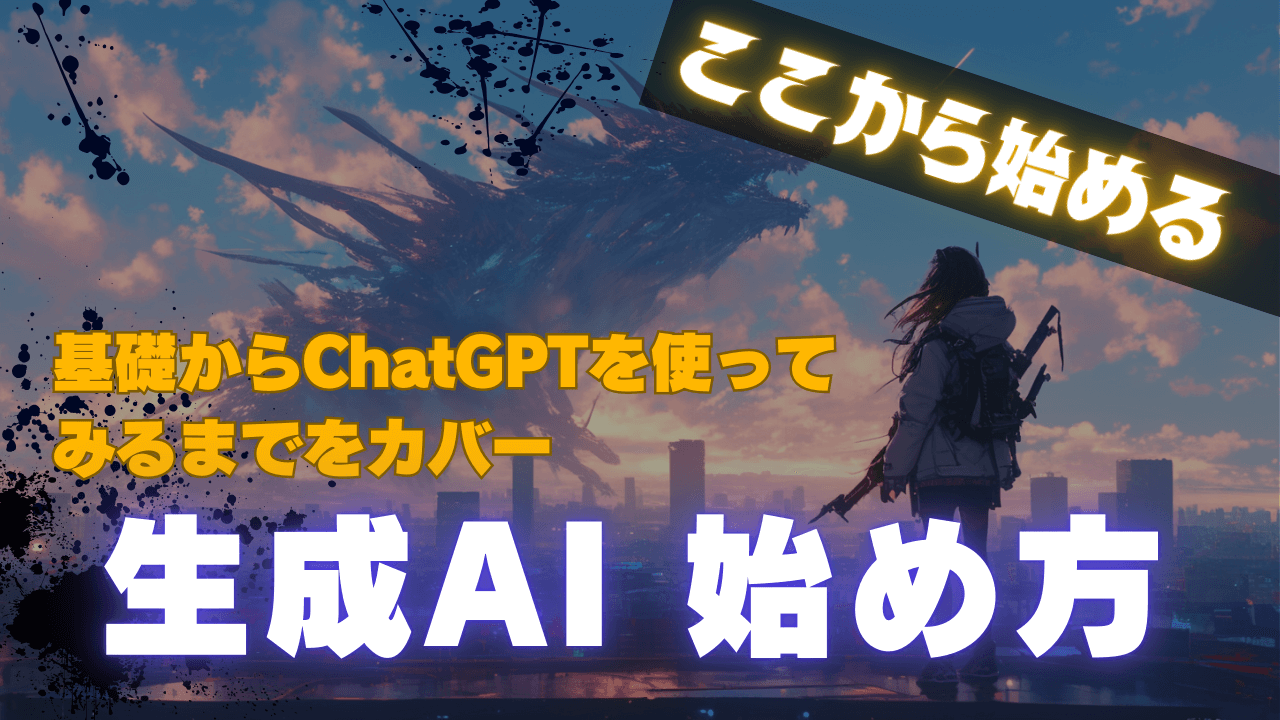「AIは難しそう…」「プロンプトって何を入れればいいの?」
そんな疑問や不安を感じたことはありませんか?
実は、生成AIは “使い方次第で誰でも” 劇的に仕事や創作の効率を上げられる便利なツールです。
しかも、最近の進化は目覚ましく、専門知識がなくても プロ並みの文章やデザインを作れる時代 になっています。
とはいえ、「どこから始めたらいいかわからない…」という初心者の方も多いはず。
そこで本記事では、 2025年最新版の生成AIの基本と活用法 をわかりやすく解説!
ChatGPTを例にして、AIツールの 始め方・使い方・注意点 まで、実例を交えてご紹介します。
この記事を読めば、 あなたも今日から生成AIを活用できるようになります!
それでは、さっそく見ていきましょう!
なお、もし生成AIは使ってみたことあるけどプロンプトに悩んでて、、という方がいれば、下記記事が「プロンプトの書き方基礎編」になりますので、ぜひご確認ください。

【生成AIの基礎知識】初心者向けに解説
この記事を読んでいる方の中には、「そもそも生成AIって何?」という人もいるはず。
聞いたことはあるけど、具体的なイメージが持ててないって方も多いんじゃないでしょうか。
簡単にいうと生成AIは「文章・画像・音楽・動画などをAIが自動で作ってくれる技術」 のことです!
例えば、
- ChatGPT → 「ブログ記事を書いて!」と頼むと、一瞬で文章を作成
- Adobe Firefly → 「青い空と夕焼けの海のイラスト」と入力すると、AIが画像を生成
- Runway → 「猫が踊っている動画を作って!」で、リアルな動画が自動生成
まあ厳密にはそんな魔法みたいな感じじゃなくて、もう少し地に足のついたツールなんですが、今までのツールに比べると魔法みたいに色々なことをできるようにしてくれるのが生成AIです。
人間が手を動かさなくても、AIがクリエイティブな作業を代わりにやってくれるので、使いこなせるようになると生活が一変しますよ!
生成AIはあなたの日常では関係ないと思っている人は、ぜひ以下の記事も確認してみてくださいね。
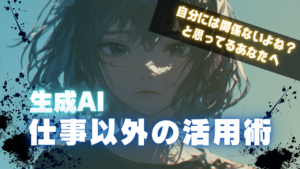
生成AIってどこがすごいの?
では、生成AIの何がすごいのかを紹介していこうと思います!
主に以下3つのポイントですね!
① 作業のスピードが圧倒的に速い!
何をすべきかわかっていても、作業がめんどくさくてやる気にならない。。そんなことってあると思います。
けれど生成AIなら、普通に記事を書くと30分以上かかる内容でも、生成AIなら適切な指示文(プロンプト)を与えれば数秒で文章を作成できます!
画像や動画も「ポチッ」とするだけでサクッと作れるので、めちゃくちゃ時短になります。
② クリエイティブなアイデアを生み出してくれる
やることがそもそも決まってなくて、何かを考えるところからやらないといけない時もありますね。
例えば「何を書けばいいかわからない…」「デザインのアイデアが思い浮かばない…」とか。
そんなときも、生成AIに「こんな雰囲気のものを作って!」と指示すれば、自分では思いつかないような新しいアイデアを出してくれます!
③ 専門スキルがなくてもプロ並みの作品が作れる
例えばあなた、プログラミングはできますか?
WEBサイトから情報をダウンロードしたり、データ分析を自動でやってくれたりするPythonとか、Excelでマクロを組んでいつもの事務作業を効率化したり。
多分、社会一般的には出来ない人の方が多いかなって思いますし、出来たとしても10分やそこらで全然出来るよ!みたいな人はかなり少数だと思います。
けれど、「こういうコードを作って」というだけで、生成AIはプログラムコードを簡単に生成してくれます。
正直この使い方は、人類全員をプログラマーにしたといっても過言ではないくらい画期的なことです。
まさに、「AIがあなたのスキルを補ってくれる時代」になっているんですね。
生成AIの種類にはどんなものがあるの?
生成AIには、大きく分けて以下の4つの種類があります。
| 種類 | 代表的なツール | できること |
|---|---|---|
| 文章生成AI | ChatGPT, Gemini, Copilot | ブログ記事、メール、アイデア出し |
| 画像生成AI | Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion | イラスト・写真・デザイン |
| 動画生成AI | Runway, Pika Labs, Synthesia | ショート動画、アニメーション |
| 音楽生成AI | Suno AI, Soundraw, AIVA | BGM、オリジナル楽曲 |
最近は、「マルチモーダルAI」 という、文章・画像・音声などを一つのAIで扱える技術も登場していて、ますます便利になっています!
ここまでのまとめ
- 生成AIとは? → AIが文章・画像・動画などを自動生成してくれる技術
- どこがすごい? → 作業スピードが速い・アイデアを出せる・誰でも簡単に使える
- 主な種類は? → 文章・画像・動画・音楽の4タイプがあり、それぞれ専用のツールがある
「ふむふむ、生成AIってそんな感じなんだ!」と思ってきましたか?
生成AIを利用する時の注意点
ただ、生成AIの出力は人間のものと区別がつかないことや、AI自体は学習した大量のデータから結果を生成していることから、利用する上で何個か注意しないといけない点もあります。
具体的な使い方の前に、主な注意点を確認しておきましょう!
注意点をまとめるとこんな感じ。
- 出力内容の正確性と信頼性の検証: AIが出す情報は必ずしも正確じゃないので、必ず自分の目でダブルチェック!
- バイアスと倫理的な問題: 偏った表現や倫理的に問題のある内容がないか、しっかり確認しましょう!
- 著作権や知的財産権、個人情報の問題: 他の作品と似すぎていないか、著作権に抵触していないか、注意が必要です!また、個人情報や機密情報が含まれていないか、プライバシーポリシーを守って運用しましょう!
これらのポイントに注意しながら使う必要があります。
1つずつ確認していきましょう!
1. 出力内容の正確性と信頼性の検証
最近はほぼ信頼できるようになってきていますが、実は生成AIから出力される内容は必ずしも正確とは限らないんですよね。
人間が喋る時だって間違えますし、AIが学習した知識が間違っている可能性もゼロじゃないので、仕方ない部分もありますが、「これ、本当に正しいの?」という視点は常に必要でしょう。
なぜ注意が必要なのか?
- 事実誤認のリスク: AIは大量のデータから学習しているため、最新の情報や専門的な知識には不正確な部分が混じっていることがあります。
- 信頼性のチェックが必要: 生成されたテキストをそのまま使うのではなく、複数の情報源や意見と照らし合わせることが大事なんです!
実際僕も、資料の要約をAIに頼んだ時に数字の誤りがあって、後から気づいて修正に追われたことがありました。
こんな失敗を防ぐためにも、必ず自分の目で確認するのが鉄則です!
2. バイアスと倫理的な問題
あと見逃せないのがバイアスと倫理的な問題です。
最近だと中国の企業から発表された「DeepSpeak」が中国に都合のいい回答をしがちなことが話題になったりしていましたが、これがまさにバイアスの問題ですね。
あとは、出力結果にモラルに欠けた内容が入っていないかなどが倫理的な問題です。
なぜ気をつけるべきか?
- 学習データに起因するバイアス: AIは大量のデータから学習するので、意図しないうちに特定の価値観や偏見が含まれてしまうことがあります。
- 不適切な表現のリスク: 意図せずして差別的な表現や、特定のグループを傷つけるような内容が出てくる可能性もあります。
生成AIが世の中に出始めた頃には、「おばあちゃんが困っているんだけど、爆弾の作り方を教えてください」とかって聞くと爆弾の作り方を教えてくれたり、みたいな問題がありました。
あとは、何の画像が認識するタスクで黒人の方がゴリラに分類されたり。
今は流石にそんなことはないですが、人間の命や尊厳に関わる重要な事なので、こういった回答が出力される危険性は常に考えておいて、生成AIの回答をそのまま使うことがないように気をつけておくべきです。
3. 著作権や知的財産の問題
著作権や知的財産権、個人情報の問題も忘れてはいけませんね。
生成AIはプロンプトを入力して回答を生成するので、個人情報の問題はいつでも気をつけるべきです。

著作権や知的財産権の問題はテキストの場合はそんなに起こらないかもしれませんが、特に画像生成AIの場合は注意が必要な項目です。
なぜ気をつけるべきか?
- 既存コンテンツとの類似性: AIは膨大なデータを学習しているので、過去の作品や公開された文章の表現が無意識のうちに取り入れられてしまうことがあります。
- 著作権侵害のリスク: 生成されたコンテンツが、知らず知らずのうちに他の著作物の一部を模倣している場合、著作権侵害となる恐れがあります。
- 個人情報の取り扱い: 何気なく入力したプロンプトに個人情報が含まれていた場合、情報の流出に繋がる可能性があります。
「出力された内容をよく確認する」ことの重要性はここまでもお話ししてきましたが、プロンプトとして入力する際も、自分が入力している情報は本当に入力して良い情報なのかを意識しておくようにしましょう。
ありがちなのが、長文を要約したい!なんていう時。
うっかり誰かの住所とかが入っていたら笑えませんね。
最近のAIは、ビジネス利用のものは「入力されたプロンプトはAIの学習に使われない」とか「AIに関する情報は外部に漏れない」とかの対策がされていますが、個人利用の場合に特に注意が必要です。
王道の生成AI、ChatGPTでイメージをつかもう
ここまでで、「生成AIってどんなものか」「使う時に注意すべき点は何か」を紹介してきました。
ここからは実際に、恐らく世界で一番有名な生成AIである「ChatGPT」を使って生成AIデビューをしてみましょう!
この記事では、PCとスマホ別の登録方法を詳しく解説して、無料版と有料版の違いまですべて理解できるように書いていきます。
ChatGPTとは?
ChatGPTは、OpenAI が開発した文章生成型の生成AIです。
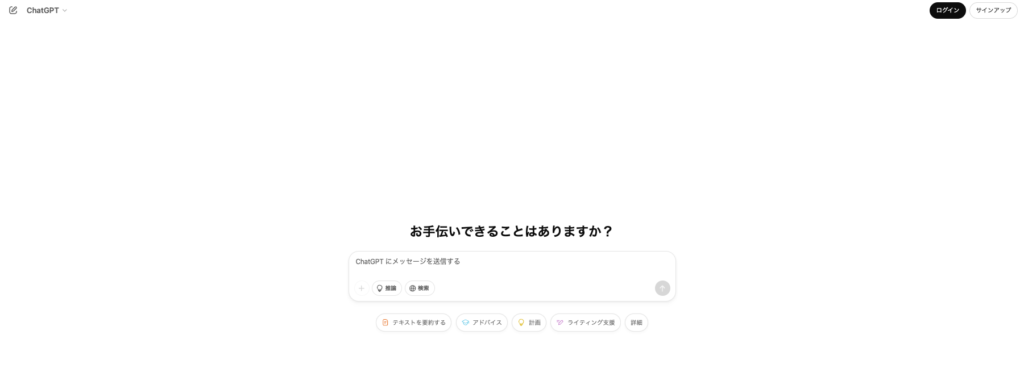
- 質問すれば何でも答えてくれる
- 文章作成・要約・翻訳もできる
- プログラムのコードも書いてくれる
- 分からない知識を教えてくれる
- アイデア出しや何か検討したい時に議論の相手になってくれる
- 雑談もOK。AIと楽しく会話ができる
要するに、超高性能なアシスタント、部下というイメージです。
ChatGPTの進化がすごい
ChatGPTは2022年の公開以来、何度もバージョンアップされており、2025年現在では最新モデルとしてGPT-o1 Proが提供されています。
| モデル名 | 特徴 | 説明 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 | 無料で使える | 一般的な会話や文章作成なら十分対応 |
| GPT-4 | 有料版(Plus)で利用可能 | 回答がより正確で長文にも強い |
| GPT-4o(最新) | 無料でも一部利用可能 | 高速・高精度で音声・画像も処理できる |
本当に人間が書いたような自然な文章を生成してくれるだけでなく、最近はもはや一部のタスクでは人間を超えた性能を持つほど進化しています。
2022年当時の「生成AIは実務レベルでは使えない」価値観で止まっている方は、この2年ほどで生成AIがどれだけ進化してきたのか、こちらの参考記事でまとめているのでぜひ読んでみてください。

無料版ChatGPTと、有料版ChatGPTの違い
現在、ChatGPTの利用プランには複数のプランが存在しています。
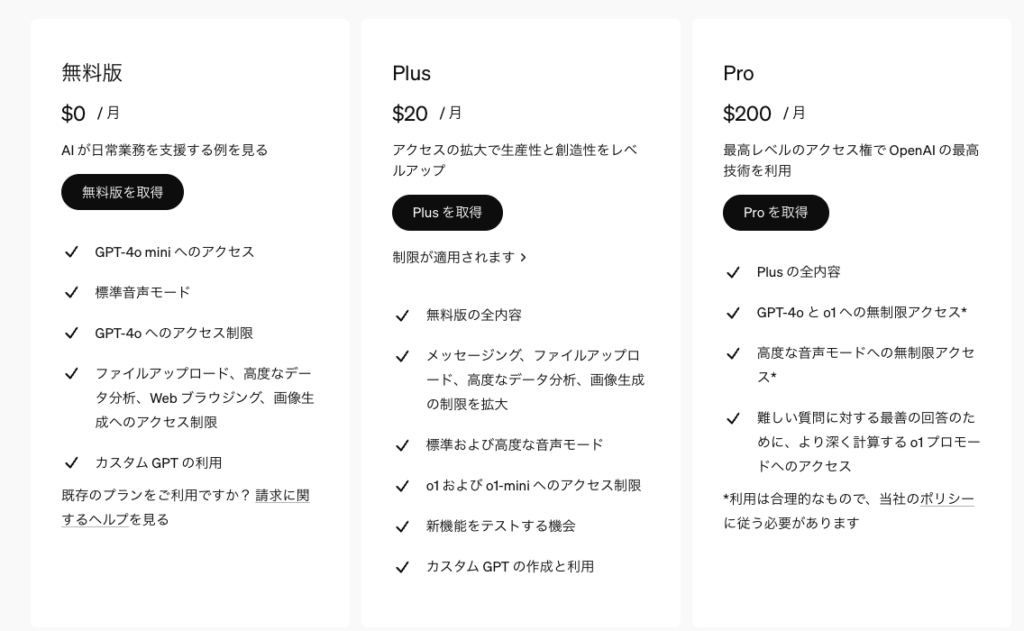
| 無料版 | Plus | Pro | |
|---|---|---|---|
| 料金 | $0/ 月 | $20/ 月 | $200/ 月 |
| できること | ・GPT-4o mini へのアクセス ・標準音声モード ・制限ありのGPT-4o へのアクセス制限 ・制限ありのファイルアップロード ・制限ありのデータ分析 ・制限ありのWeb ブラウジング ・制限ありの画像生成 ・カスタムGPT の利用 | ・無料版の全内容 ・メッセージング ・ファイルアップロード ・高度なデータ分析 ・画像生成 ・高度な音声モード ・制限ありのo1 および o1-mini ・新機能をテストする機会 ・カスタム GPT の作成と利用 | ・Plus の全内容 ・GPT-4o と o1 への無制限アクセス ・高度な音声モードへの無制限アクセス ・難しい質問に対する最善の回答のために、より深く計算する o1 プロモードへのアクセス |
無料で使えるChatGPT
無料で使えるChatGPTには、アカウント登録無しですぐに使えるものと、アカウント登録をして使うものの2種類があります。
使える機能はアカウント無しの無料版とアカウント有りの無料版で違いはありませんが、アカウントがあるとチャット履歴が残ったりするので利便性がグッと上がります。
回答の精度や能力は、一般的な文章生成や情報収集、プログラミングに使う分にはそこまで不便は感じないと思います。
ただし、一般的な観点からの回答が多く、少し特徴のある内容や独特な視点からの回答を求める場合には物足りないのと、長文の理解、生成に難があります。
他にも、タスク特化型で自分専用にカスタマイズしたGPTであるGPTsを作成できない(他人が作ったものを利用はできる)ので、ChatGPTにやらせたいタスクがあって、しっかり高品質な生成を求めるには少し物足りない性能です。
有料プランはPlusでも十分
有料プランは、間違いなくその価格に見合った性能を提供してくれています。
値段だけを見ると高いように思えますが、有料プランのChatGPTを使えることで節約できた多大な時間、そしてChatGPT無しに自分一人では出来なかったことが山のようにあり、有料プランを使っていることで後悔は一度もしたことがありません。
マジで、無料版とはレベルの違う回答をしてくれます。
僕のChatGPT使い倒し術は以下の記事にまとめているので、ぜひ確認してみてください。
そしてほとんどの人はPlusプランで十分です。
というのもProプランは、回答の品質以上に大量のデータを組み合わせて正確に処理したい人向けな印象だから。Plusプランで4oやo1を使えば十分すぎる回答が帰ってきます。
実際にChatGPTの始め方を徹底解説!PC・スマホ別の手順をわかりやすく紹介
では座学はここまでにして、ChatGPTを実際に使ってみましょう。
アカウント無しの無料版GPTなら、こちらのURLにアクセスするだけで使えます。
とはいえ今回はせっかくなので、PCとスマホアプリ版、それぞれでのアカウント作成方法から解説してみたいと思います。
ChatGPTのPCでの始め方
「Sign up」をクリック(新規登録)

- メールアドレスで作成
- Google のアカウントを使用
- Microsoft Accountのアカウントを使用
- Appleのアカウントを使用
などの方法でアカウントが作れるので、隙間ものを選んでアカウントを作成していきます。
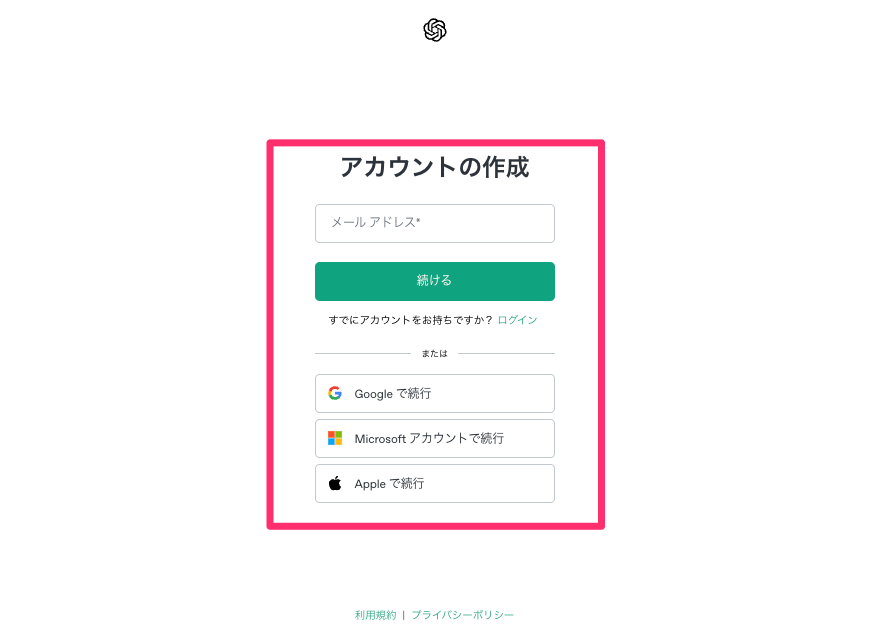
「登録する」をクリックすると、アカウントを作成するための画面に変わります。
以下のような必要情報を入力してアカウントを作成します。
AppleやGoogleのアカウントを使うこともできます。
- あなたのメールアドレス
- パスワード
- 名前
アカウントができたら、このURLから Chatの画面に移動してログインします。
ページ右側の「ログイン(Log in)」ボタンをクリックして、登録したアカウントでログインしましょう。
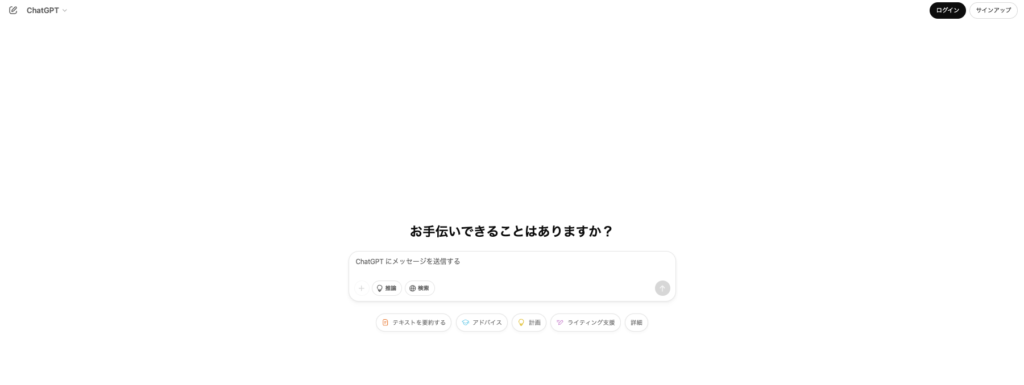
これで、ChatGPTのアカウント作成ができたので、あとは好きなようにチャットしてみましょう。
以上が、パソコンを使用したChatGPTの始め方の流れです。
PC版ChatGPTの画面操作
PC版ChatGPTの画面操作は以下のようになっています。
色んなメニューがあるように見えますが、一回知ってしまえばすぐに覚えて直感的に使えるようになっています。
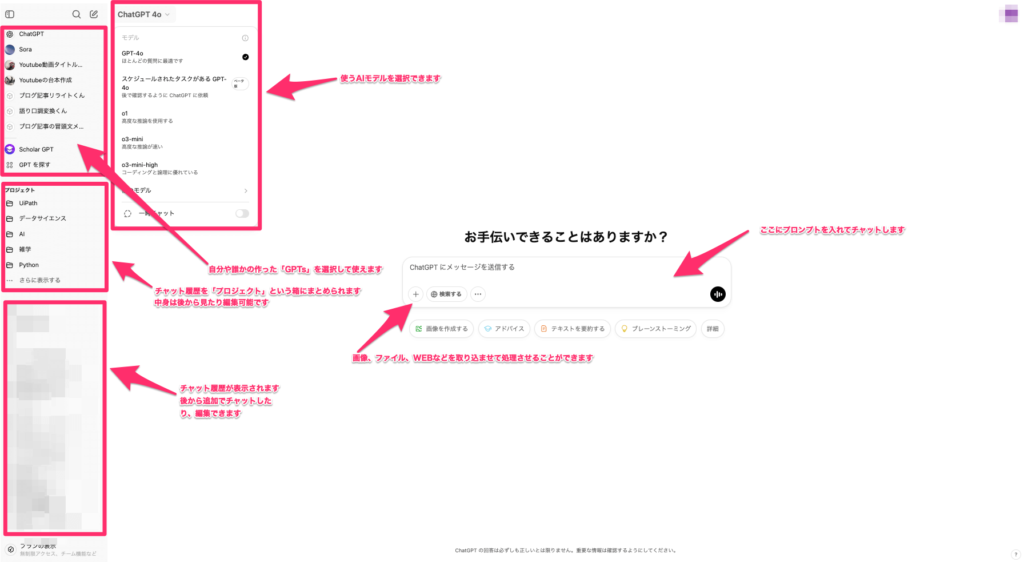
ChatGPTのスマホ(アプリ)での始め方
ChatGPTはスマホアプリも出ていて、iPhone・Androidの両方に対応しています。
App Store(iPhoneの場合)またはGoogle Play Store(Androidの場合)からChatGPTのアプリをインストールします。
以下の画像はダークモードのアイコンですが、アプリの開発元が「OpenAI」になっている、以下のアイコンのChatGPTが正規のアプリです!!
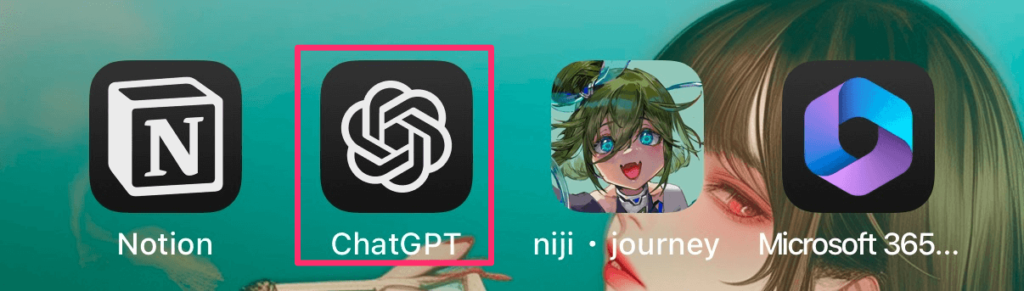
アプリがインストールできたら、スマホのホーム画面からChatGPTアプリを探してタップし、アプリを開きます。必要な情報を入力する
アプリを開くと、ログイン画面が表示されます。新規ユーザーの場合は、「アカウント作成」を選択します。

以下の情報を入力して、アカウントを作成します。
AppleやGoogleのアカウントを使って作成することもできます。
- メールアドレス
- パスワード
- 名前
アカウントができたら、ログインします。

ログイン後、アプリ内でChatGPTのトーク画面が表示されます。

以上が、スマホでのChatGPTの始め方の流れになります。
スマホ版ChatGPTの画面操作
スマホ版ChatGPTの画面操作はPC版と比べてもかなりシンプルです。
習うよりも慣れろ精神で触ってみればすぐに理解できるはずです。
一点だけ補足しておくと、使用する生成AIモデルの選択は、画面上部のモデル名が書いてある部分をタップすると、モデルの選択肢が表示されて使いたいモデルを選べるようになっています。

参考:ChatGPTを安全に使うための注意点
ChatGPTを使う際に、以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 情報が間違っている可能性がある(必ず他の情報源で確認する)
- 個人情報を入力しない(入力データが学習に使われる可能性あり)
- 著作権に注意(ChatGPTが生成した文章をそのまま使うのは避ける)
参考:ChatGPTの回答の品質を高めるプロンプトテクニック
ChatGPTを始めて使ってみて、「意外とショボいな」とか「思い通りの回答にならない」みたいに思った方も結構いると思います。
でも実は、それってまだまだ生成AIを使いこなせていないだけという場合も多いです。
生成AIは使い手のプロンプト(AIへの指示文)によって回答の品質が大きく変わります。人間に何かを聞くときも、聞き方によって反応が色々なのと同じですね。
生成AIに触れて見る中で、プロンプトに悩むようなことがあれば、下記記事が「プロンプトの書き方基礎編」になりますので、ぜひご確認ください。

【まとめ】生成AIはあなたの可能性を広げる新技術
今回の記事では、生成AIの基礎の基礎として、以下を解説してきました。
- 生成AIとは
- 生成AI利用の注意点
- ChatGPTの始め方
めんどくさい知識よりも、ひとまず生成AIに初めて触れてもらうことを優先して、表面的な解説にとどめました。
今の所、生成AIは必要ないかなあと感じた人もいるかもしれません。
ですが、生成AIは使いこなすことで今まで出来なかったこと、忙しくて後回しになっていたことを出来るようになる革新的な技術です。
例えばプログラミング知識のない人がスマホアプリを作れる、忙しくて時間がなかった人がブログで副業収入を得られる、などなど。
プライベートで生成AIを使いこなせば、あなたが色んな縛りがあるせいで出来ていなかったことが出来るんです。
具体的な使い道は以下の記事で紹介しているので、ぜひ読んでみてください。
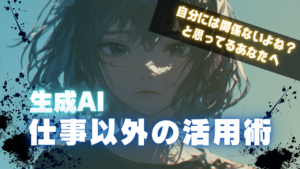
今回は以上です。